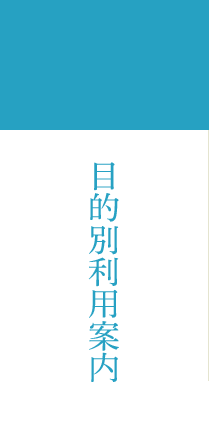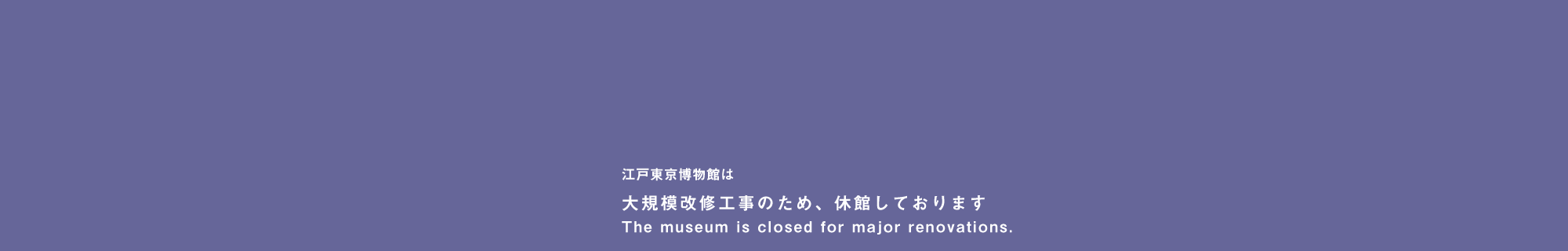
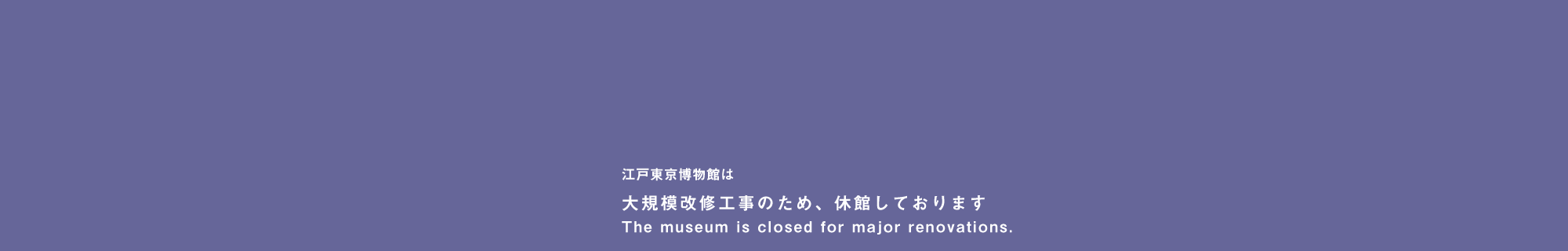
2015年度
2016/03/18
上野動物園『動物園グラフ』
153号(江戸東京博物館メールマガジン 2016/3/18 173号掲載)
日増しに暖かくなり、花の便りも聞かれるようになりました。桜の名所として 知られる上野恩賜公園の中、日本で最初の動物園として1882(明治15)年の 開園より130年以上もの間、多くの人に親しまれている東京都恩賜上野動物園。その飼育動物を紹介する『動物園グラフ』には、戦前の“ゾウの花子”の姿や、戦後こどもたちに人気を博した“おさる電車”の愛らしい写真が掲載されています。どんな時代も私たちを楽しませ、癒し、時に元気づけてくれた動物たち。上野動物園の長い歴史は、東京の歴史とも重なります。
※当室所蔵の『動物園グラフ』は、東京市役所発行1937年(再版)、1938年(4版)、1940~1942年(10~13版)、1942年(15版)、東京動物園協会発行1952年(70周年記念号)、1961年、1982年(開館100周年号)、1988年の11冊です
2016/03/18
『イタリア使節の幕末見聞録』
152号(江戸東京博物館メールマガジン 2016/2/19 172号掲載)
現在江戸東京博物館では、1階特別展示室において日伊国交樹立150周年を記念して 特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ―天才の挑戦」が開催されています。
今年で150周年を迎える日伊の国交は、日伊修好通商条約の締結により始まりました。
この条約はペリーが浦賀に来航した1853年から数えて13年後、明治時代の誕生を目前とした江戸終焉の時期にあたる1866年に締結されました。条約締結のために 使節として来日したヴィットリオ・アルミニヨンが記した日本見聞録が、『イタリア使節の幕末見聞録』として翻訳され、現在でも読むことができます。西国から遠路はるばる来日した使節の目に、幕末の日本はどのように映ったのでしょうか。幕末の日本を少し異なる角度から体験する事のできる1冊です。
また、異国との条約締結に不可欠な外交文書、『黒船来航日本語が動く そうだったんだ!日本語』では この外交文書に光があてられています。幕末の通詞たちにのもとへやってきた外交文書という黒船、幕末通詞たちの奮闘の様子を垣間見る事ができる1冊です。ぜひ、併せてご覧下さい。
・『イタリア使節の幕末見聞記』 V.F.アルミニヨン 新人物往来社 1987年(請求記号:2105/248/87)
・『黒船来航日本語が動く そうだったんだ!日本語』 清水康行/著 岩波書店 2013年(請求記号:8102/32/0013)
2016/01/18
『宮中のシェフ、鶴をさばく』
151号(江戸東京博物館メールマガジン 2016/1/15 171号掲載)
お正月には鶴がデザインされたものを多く見かけます。そんなおめでたい象徴である鶴も、今や希少となり、特別天然記念物に指定されています。
今は鶴を食べる習慣はありませんが、『本朝食鑑』という元禄期に刊行された本草書には、鶴を食するとどのような効果があるのかが詳しく書かれています。江戸時代、健康を保つのに適し、めでたい象徴でもあったので、将軍は鷹狩を行い、鶴を捕え、天皇に献上していました。また、将軍家や大名の間で饗応、贈答などに用いていました。
『宮中のシェフ、鶴をさばく 江戸時代の朝廷と包丁道』(西村慎太郎 著,吉川弘文館,2012年)は、天皇や公家、将軍家や大名の前で、大切な鶴をさばく儀式である「鶴包丁」を務めた人々や、「包丁道」と呼ばれた厳密な作法を守り、家職となった四条家についてなど、興味深いテーマで語られている一冊です。
2015/12/20
『大(Oh!)水木しげる展』図録
150号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/12/18 170号掲載)
去る11月30日、漫画家・水木しげる先生が93歳で逝去されました。
ガキ大将としてのびのびと過ごし、妖怪や精霊に興味を持った鳥取での少年時代。
画家を志した青年時代に太平洋戦争下ラバウルへ出征。終戦後、紙芝居作家や貸本作家を経て漫画家に。『ゲゲゲの鬼太郎』をはじめとする妖怪漫画の第一人者であるとともに、『総員玉砕せよ!』など激戦地での壮絶な経験をつづった戦記ものも多く手がけました。
『大(Oh!)水木しげる展』は、2004~2005年に全国を巡回し、江戸東京博物館でも開催された展覧会です。当代きっての水木ファンである荒俣宏、京極夏彦両氏が「水木しげるが喜ぶ企画展」という基本テーマを掲げて監修し、老若男女に親しまれた水木しげるの「人」と「作品」の魅力に迫りました。幼少期に影響を受けた地獄極楽絵図、十代で描いた童話絵本や貴重な水木作品をはじめ、妖怪絵巻や人形・仮面コレクションなどがずらりと並ぶ充実した内容の図録も刊行。
各関係者より寄せられた文章からも溢れんばかりの“水木愛” が伝わります。
生涯好きな道を歩み「気がついたら幸せになっていました」と語った水木氏の水木しげるたる所以をうかがい知ることができる一冊となっています。
『大(Oh!)水木しげる展』図録(朝日新聞社 2004年)
[関連リンク]
水木プロダクション公式サイト http://www.mizukipro.com/![]()
大(Oh!)水木しげる展 https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/s-exhibition/special/1803/大oh水木しげる展/
※展覧会は終了しています。
2015/11/27
『ニァイズ Nya-eyes』(東京都写真美術館ニュース)
149号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/11/20 169号掲載)
現在(2015年11月20日)、図書室では特別展『浮世絵から写真へー視覚の文明開化』に関連して、東京都写真美術館図書室との協力企画『写真の魅力発見!』(~2015年12月13日(日))を特集コーナーとして設置しています。
写真美術館は大規模改修工事休館中(~2016年8月末予定)ですが、今回は休館中も発行されている写真美術館ニュース『ニァイズ Nya-eyes』をご紹介します。
これは、学芸員や司書をはじめとする実在の職員が登場し、漫画のキャラクターとともに美術館の活動についてわかりやすく教えてくれる月刊広報紙です。2011年の創刊号から39号までをまとめて単行本として刊行するなど、美術館のメディアミックスとしてはユニークな試みといえるのではないでしょうか。
そのほか写真美術館の展覧会図録や、本家(?)写真美術館ニュース『アイズ eyes』(創刊号から33号までは『東京都写真美術館ニュース』)なども所蔵していますので、特別展にお越しの際にはぜひご覧ください。
『ニァイズ Nya-eyes』(東京都写真美術館ニュース)カレー沢薫著 講談社 2014年 請求記号:M3653/TO-4/197
東京都写真美術館HP http://www.syabi.com/
2015/10/16
『体感!東京凸凹地図』~東京の凸凹を感じる~
148号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/10/16 168号掲載)
江戸東京の地図本はずっとコンスタントに出版されています。地図をあつかっていますので、判型が大きくて、「ムック」のかたちで出されているものも多いです。
古地図を現代地図と比べる、というテーマの本が主流で、これらは東京歩きのガイドブックとしても一役買ってきました。
さて、今回紹介する地図本『体感!東京凸凹地図』(東京地図研究社編著・技術評論社・2014年)は、東京歩きのためにまた一味違った役割を演じてくれそうです
収録されている地図・写真をみると、凸凹が感じられるように作製されているのです。
じっと見ていると、台地が、段丘が、尾根が盛り上がって見えてくるという……何とも不思議な感覚です。“本書を片手に実際の凸凹を体感してもらいたいと思います”と文中にありますが、地理・地学の分野から専門的に書かれてもいて、見ごたえ読みごたえがあります。
2015/09/29
『耳袋(耳囊)』
147号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/9/18 167号掲載)
現在開催中の企画展「くらべてみよう江戸時代」(~9月27日)で展示されている随筆集『耳袋』をご覧になりましたか?
『耳袋』というと怖い話だと思う方もいらっしゃいますが、それは『新耳袋』(1990年及び、1998年から発行された現代百物語)の影響でしょう。
江戸時代後期、南町奉行の根岸鎮(やす)衛(もり)が聞き記した『耳袋』は怖い話だけでなく、人情話や人生訓、病気の治療法に至るまで、実に多彩なジャンルの話が収録されています。
出版はされませんでしたが、写本によって世に出回りました。武士や町人など様々な人から聞いた噂話を集めており、当時の人びとが何を考え、どう感じたかを知ることができます。ひとつの話が短く、飾らない文章が読みやすいので気軽に読めるところもオススメです。
図書室では、読みやすい書き下し文や現代語訳の本をご用意しています。
手に取ってじっくり読んでいただけます。読書の秋、芸術の秋、ぜひ展示と併せてご覧ください。
『耳袋1・2 東洋文庫207・208』根岸鎮衛/著 鈴木棠三/編注 平凡社(1986年)
『耳袋 上・下巻 岩波文庫』根岸守信(鎮衛)/著 柳田国男,尾崎恒雄/校訂 岩波書店(1939年)
『耳袋 教育社新書原本現代訳 60』根岸鎮衛/著 長谷川政春/訳 教育社(1981年)
2015/09/02
『おみやげと鉄道』
146号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/8/21 166号掲載)
夏休みも残りわずかとなりました。長期の休暇を利用して少し遠出をした方、お近くで夏のイベントを楽しんだ方、それぞれの胸に楽しい夏の思い出が刻まれたことと思います。
夏休みの終わりとともにやってくるのがお土産たち。
間もなく、各地を旅した友人たちからの思い出話とともに、綺麗にパッケージされた土地のお菓子たちが私の心と胃袋を満たしてくれることでしょう。
さて、このお土産たち、それぞれに様々なエピソードを持っている事をご存じでしょうか?私が個人的に大好きな仙台のお菓子。このお菓子は、かつて仙台発の飛行機にて機内食に採用されていたとのこと。
航空機利用客に支持されたことにより、全国的な知名度を獲得したそうです。
『おみやげと鉄道』(鈴木勇一郎/著 講談社 2013年 請求記号:6895/3/0013)では、その他にも伊勢参りの名物や、小鳥の形のお饅頭などのたどってきたエピソード、その裏に隠された歴史とのかかわりなどを紹介しています。何気なく口にしているお菓子たちの背景に少し目を向けることのできる1冊です。
2015/09/02
『富士山百画』
145号(江戸東京博物館メールマガジン 2015/7/17 165号掲載)
一昨年、信仰の対象であり芸術の源泉であることが評価され、世界文化遺産登録をされた富士山。
『富士山百画』は、登録が決まる少し前に、「富士山世界文化遺産登録推進両県合同会議」(“両県”はもちろん、静岡県と山梨県です。)より発行された画集です。
一度は見たことがあるような、代表的な100作品で構成されており、当館のテーマとも関わりの深い「熈代勝覧」や「江戸一目図屏風」、浮世絵、狩野派の作品なども掲載されています。
最古のものは、1069年に描かれた「聖徳太子絵伝」の富士山。
100点目は横山大観の大正時代の作品ですが、99点目を見ると、棟方志功が1965年に制作したものです。
実に900年にも渡り、途切れることなく描き続けられた富士山。
こうして1冊にまとまると、日本人にとって富士山は特殊な意味を持つ存在であり、それは現代まで脈々と受け継がれているとあらためて実感します。
2015/06/23
変わり咲き朝顔を楽しむ
144号 (2015/06/19 江戸東京博物館ニューズレター 164号掲載)
2013年夏に当館で開催された特別展「花開く江戸の園芸」では、前売りチケットにあわせて“変わり咲き朝顔(変化朝顔)”の種を頒布しました。
我が家でも栽培に挑戦。龍が爪を丸めた様な形の葉っぱに小指の爪ほどの小さな赤い花、白く清楚な八重咲の朝顔…と、ひと夏の間に様々な花や葉がベランダを彩り、毎朝わくわくしながらその成長を楽しみました。
江戸の園芸ブームの中でも独特のジャンルを形成し、武士から町人まで多くの人びとを夢中にさせた朝顔。江戸時代後期から明治大正にかけて幾度かの朝顔ブームが起こり、花びらが細長くしだれたもの、フリルのような牡丹様の花など、突然変異の変化朝顔が競うように栽培されました。
『江戸の変わり咲き朝顔』や国立歴史民俗博物館の図録『伝統の朝顔』シリーズでは、歴史や芸術、栽培方法など変化朝顔の世界を深く知ることができます。
これが朝顔?!と驚くばかりの変化朝顔の数々をぜひお楽しみください。
・渡辺好孝『江戸の変わり咲き朝顔』平凡社 1996年(請求記号:6274/1/96)
・『伝統の朝顔1~3』国立歴史民俗博物館 1999-2000年(請求記号:M35/KO-2/79-1~3)
・『朝顔図譜をよむ-あさかほ叢-』国立歴史民俗博物館 2008年(請求記号:M35/KO-2/155)
(参考)『花開く江戸の園芸』東京都江戸東京博物館 2013年(請求記号:M3624/TO-3/371-S0)
[関連リンク]
・国立歴史民俗博物館“くらしの植物苑”
→歴博では、今夏も特別企画「伝統の朝顔」が開催されるそうです! http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/
・九州大学大学院 理学研究院 生物科学部門 染色体機能学研究室 http://mg.biology.kyushu-u.ac.jp/
2015/06/08
『歌舞伎オン・ステージ』シリーズ(白水社)
143号 (江戸東京博物館メールマガジン 2015/5/15 163号掲載)
常設展示室では歌舞伎『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の衣裳や小道具などを展示しています。
江戸きっての男伊達・助六と、その恋人の揚巻が中心となり、花の吉原を舞台に展開するこの芝居の初演は正徳3年と言いますから、今から300年ほどさかのぼります。
もとは3時間を超える大作ですが、現在ではかなり省略されて上演されることが多いようです。
どんな物語か詳しく知りたくなったら、図書室で『歌舞伎オン・ステージ』シリーズ(白水社)のうち『助六由縁江戸桜』の巻をご覧になってみてください。台詞だけでなく注釈や解説のほか芸談も掲載されています。
ところで助六は実は曽我五郎の仮の姿なのですが、この巻には『寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)』も収録されていますので、比べてみるのも面白いでしょう。
2015/05/12
「流行」を通してみる戦後史
141号 (江戸東京博物館メールマガジン 2015/3/20 161号掲載)
3月28日、いよいよ常設展示室がリニューアルオープンします。江戸城の模型や ミュージアム・ラボ(体験コーナー)が新設されるなど、より充実した展示へと 生まれ変わります。その中で新たに1960年代から2000年代までの生活や文化の 展示コーナーが設けられます。改めて振り返り懐かしく思う方もいれば、 新鮮に感じる世代もあるかと思います。記憶に新しい時代だけに、興味深く ご覧いただけるのではないでしょうか。
下記の3冊の資料は戦後の混乱を乗り越え、高度経済成長期から現代に至るまでの 「流行」をみることができます。身近なものを通して時代をみると、当時の 雰囲気を生き生きと感じることができます。ぜひ展示と併せてご覧ください。
・往年のスターから現在も活躍しているアイドルまで、時代の「顔」が 収録されています。
『「明星」50年601枚の表紙』明星編集部/編 2002年(請求記号:0516/3/002)
・流行は繰り返すといいますが、ファッションはまさにその傾向が顕著に 表れています。
『ストリートファッション 若者スタイルの50年史 1945-1995 』 アクロス編集室/編 1995年(請求記号:3831/72/95)
・時代を象徴する言葉を通して、当時の世相をみることができます。
『新語死語流行語―こんな言葉を生きてきた』大塚明子/注解 イミダス編集部/編 2003年 (請求記号:8147/10/003)
2015/05/12
リニューアル展示といっしょにみてほしい団地の風景
142号 (江戸東京博物館メールマガジン 2015/4/17 162号掲載)
リニューアルした常設展示室。みなさんの印象に残るのはどこでしょう。
十人十色 だとは思いますが、一度観て、私は戦後の住い(部屋)の実寸の復元が強く残りました。1950年代の住宅に実際に靴を脱いであがる、という体験ができるミュージアム・ラボ。たたみの部屋に、くつろいで、つい長居してしまいそうです。
これより時代が少し下って、1960年代の「団地」の玄関から部屋にかけての復元。これはもう古い映画やドラマの世界からそこだけが抜け出てきたような模型です。
さて、中身はわかったけれど、外見は?ここからは図書室にある本で補填してみてください。
『団地の子どもたち』(洋泉社・2009年・請求記号3839/152/009)は、子どもたちを 被写体に、全国の団地の外観風景を収めた写真集です。主に当時のモノクロ写真から 成りますが、一枚一枚から団地という空間の雰囲気や息づかい、また子どもたちの 声まで聞こえてきそうです。