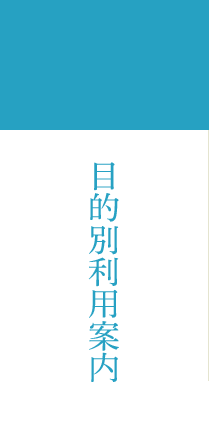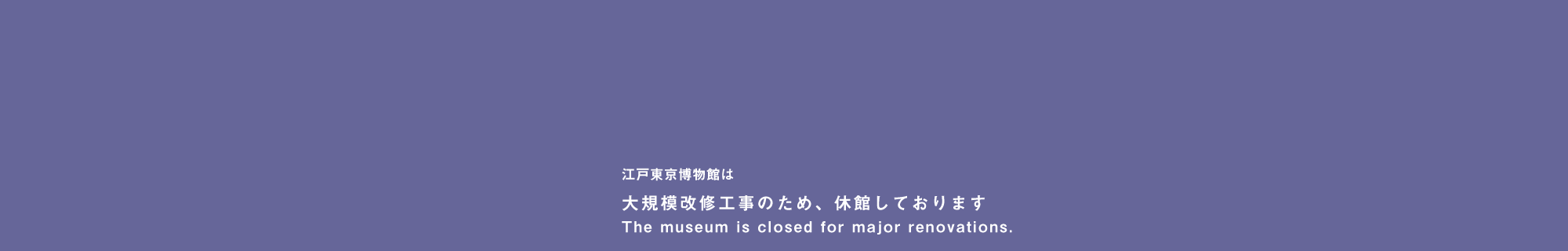
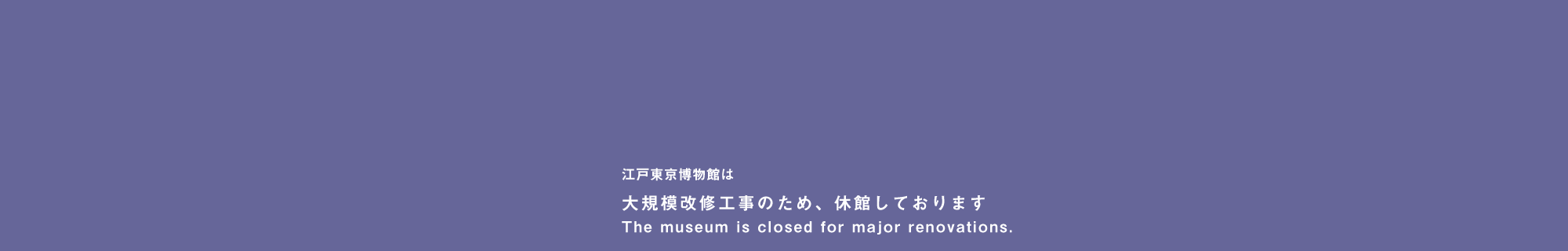
2012年度
117号 2013/3/15 (江戸東京博物館ニューズレター 137号)
『東京人』江戸東京博物館 開館記念特集号
来たる3月28日、江戸東京博物館は満20歳を迎えます。
『東京人』1993年5月号は、開館したばかりの江戸東京博物館と分館のたてもの園を取り上げた開館記念特集号として発行されました。「完全ガイド」と銘打つ通り、収蔵品や展示模型から館内の諸施設までを隈なく紹介。初代館長・児玉幸多氏、後に二代目館長となる小木新造氏、竹内誠現館長をはじめ、展示監修者の記事も並び、読み応えがあります。
そして、現在発売中の『東京人』2013年4月号の特集は“江戸東京を遊ぶ”。
開館20周年を記念して再び、江戸東京博物館特集が組まれています。
この20年間で収蔵品も増え、常設展や特別展、イベント等へ多くの方がご来館くださいました。図書室には、これまで開催された特別展・企画展の図録や調査報告書・紀要など、江戸東京博物館の刊行物を並べたコーナーがあります。
書棚にずらりと図録が並ぶ様子にも、当館が歩んできた20年を実感していただける
のではないかと思います。
・開館記念特別号 特集 江戸東京博物館完全解読100%活用ガイド
『東京人』1993年5月号(都市出版編 東京都文化振興会発行)
・特集 江戸東京を遊ぶ
開館20周年 全部見せます、江戸東京博物館 江戸東京たてもの園
『東京人』2013年4月号(都市出版編・発行)
116号 2013/2/15 (江戸東京博物館ニューズレター 136号)
『日本唱歌全集』
大学生10人に『お江戸日本橋』という唱歌を知っているかと尋ねたら、手を挙げた学生は一人もいませんでした。『日本唱歌全集』(井上武士編 音楽之友社 1998 7677/19/98)によれば、天保年間の流行歌が元歌であり、歌い出しは「お江戸日本橋ななつ立ち はつのぼり」。ある時期までの日本人には、なじみがある唱歌なのではないでしょうか。「江戸の旅立ちは朝早い」と印象づける歌です。
そういった歌も、いつしか消えてゆくのは仕方のないことなのかもしれません。しかし、一見他愛ない歌詞に、時代の事象や心情が織り込まれていることは見逃せません。
唱歌は歌って楽しむだけでなく、様々な事柄を私たちに伝えてくれます。「日本人にとって音楽の文化遺産であり、重要な記録として永久に残しておかなければならない」という著者の言葉は、時代を経てますます傾聴すべきものとなっています。
115号 2013/1/18 (江戸東京博物館ニューズレター 135号)
東京スカイツリー関連図書
図書室では「東京スカイツリー関連図書」の棚を設けています。
現在まで30冊ほどの関連本を集めています。
この中から1冊、と前々から考えていたのですが、どれもこれも甲乙つけ難く……。
ダイナミックな写真を使った本が多い中、今回はあえて絵本から(2冊)紹介したいと思います。
『図解絵本 東京スカイツリー』(ポプラ社・2012年)。こちらはタワー完成までの徹底取材にもとづき、建設の様子から機材・部材に至るまで、説明付で詳細に描かれています。ほのぼのとしたタッチの絵は、写真で見るのとは違って新しいのに何か懐かしい感覚で、大人が見ても楽しめると思います。
『しごとば 東京スカイツリー』(ブロンズ新社・2012年)もまた違ったタッチの絵で、東京スカイツリーに関わる人たちにスポットライトをあてながら描かれているところがユニークです。
棚は3月まで設けています。
114号 2012/12/21 (江戸東京博物館ニューズレター 134号)
『絵草紙屋 江戸の浮世絵ショップ』
常設展示室にある絵草紙屋の復元模型をご覧になられたことはあるでしょうか?
今では、うやうやしく額縁などに入って飾られている錦絵が、所狭しとそのまま吊り下げられたり、並べられたりしています。芝居や相撲を題材にした錦絵は、当時、大量生産され安価で、今のブロマイドのようなものでした。
『絵草紙屋 江戸の浮世絵ショップ』(鈴木俊幸著,平凡社,2010年発行)は、江戸の「今」がわかる錦絵や草紙などを扱っていた絵草紙屋の様子が、当時の戯作者の文章や絵師の作品など、さまざまな資料を通し、いきいきと紹介されています。
江戸の盛り場で庶民が楽しむ風景を目に浮かべながら、江戸文化の側面を知る興味深い一冊です。
113号 2012/11/16 (江戸東京博物館ニューズレター 133号)
『守貞謾稿』
江戸の風俗を調べるとき、“まずコレを見よ”という文献の筆頭にあげられる『守貞謾稿(もりさだまんこう)』。
作者の喜多川守貞が、江戸の事物習俗について自身の見聞のままに収集・分類し、挿図入りで解説しています。項目数は700にのぼり、例えば、家屋のつくり、湯屋(銭湯)の構造、男女の髪型、子供の遊び、諸職のさまざま、草履の値段、門松の形、刺身の盛り付け…と、なんでもござれ。
その守備範囲の広さ、細かな記述に圧倒されます。江戸に限らず、守貞が生まれ育った大坂との相違を“京坂では~、江戸では~”と、比較対象した記述があるのも特徴のひとつです。
活字翻刻された本では、東京堂出版刊行のものと岩波文庫版をオススメします。それぞれ第5巻に索引があり、江戸風俗の百科事典としてご活用いただけます。
・『守貞謾稿』全5冊
(朝倉治彦,柏川修一校訂編集 東京堂出版1992年)
・『近世風俗志(守貞謾稿)』全5冊
(宇佐美英機校訂 岩波書店1996-2002年)
※原本は国立国会図書館で所蔵。Webページ「国立国会図書館デジタル化資料」で
ご覧いただけます。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2610250![]()
112号 2012/10/19 (江戸東京博物館ニューズレター 132号)
『宮内庁書陵部書庫渉獵 書写と装訂』
『図説書誌学 古典籍を学ぶ』
先人たちから受け継いだ書物を後世に伝える事は、現代を生きる私たちにとって重要な責務です。そのためには、災害などの外的被害から守る、保存環境を適切に維持する、劣化・破損した場合の処置など、書物に対する正しい知識を持つことが大切です。
『宮内庁書陵部書庫渉獵 書写と装訂』(櫛笥節男著 おうふう 2006)、『図説書誌学 古典籍を学ぶ』(慶応義塾大学附属研究所斯道文庫編 勉誠社 2010)は、様々な形態の書物とその装訂とを紹介しています。綴じ方、製本過程、保存容器には多様な工夫があり、書かれた内容はもちろん、書物それ自体が文化遺産であると改めて気づかされます。
書誌学の専門的な知識が豊富に綴られた両書ですが、図や写真も多いので、
眺めるだけでも楽しめます。古典籍に親しむ一冊としてオススメします。
111号 2012/9/14 (江戸東京博物館ニューズレター 131号)
『八角屋根の東京駅赤レンガ駅舎』
5月の東京スカイツリーだけではありません。東京のランドマークと言うべき建造物が今年はもうひとつ。「復原」作業がつづけられていた東京駅丸の内赤レンガ駅舎が、10月に完成します。
赤レンガ駅舎は大正3(1914)年竣工、全長約330メートル、当初は全棟3階建てでドーム型の屋根がふたつ付いていました。それが、昭和20(1945)年の東京大空襲により屋根および3階部分の多くを焼失。戦後、ドーム型屋根は八角屋根に付け替えられました。
その後、新しい駅舎のはなしもありましたが赤レンガ駅舎は存続、平成15(2003)年に重要文化財に指定され、平成19年から3階建てドーム型屋根への復原作業がはじまりました。
『八角屋根の東京駅赤レンガ駅舎』(朝日新聞出版・2009年・請求記号6865/38/009)は
復原作業前、八角屋根の東京駅の最後の姿を収めた写真集です。全体、部分。外から、
内から。撮影された写真はどれも美しいものです。
八角屋根は応急の処置だったといいます。しかし、これまでの東京駅の歴史をふり返ると、ドーム型屋根の期間約30年に対し、八角屋根の期間は約60年…。
復原完成をよろこぶ一方、消えゆく(消えた)八角屋根を惜しむ気持ちに応えて。
今回はあえてこの本を。
110号 2012/8/17 (江戸東京博物館ニューズレター 130号)
『幻の東京オリンピック』
ロンドンオリンピックでは、日々熱戦が繰り広げられ、
時差のある観戦に、寝不足になられた方も多かったのではないでしょうか。
かつて、東京では1964年にオリンピックが開催されました。
しかし、それよりも前の1940年、東京オリンピックは開催されるはずだったのです。
『幻の東京オリンピック』(橋本一夫著,日本放送出版協会,1994年発行)は、
1940年に開催予定だった東京オリンピックの招致の経緯、大会準備、
そして戦争の影響で大会返上となるまでを、詳細に調査し、まとめた1冊です。
ロンドンでオリンピックが開催された折、こうした本を読んでみてはいかがでしょう。
また、図書室には、『東京オリンピック1964』(フォート・キシモト,新潮社編,新潮社,
2009年発行)など、半世紀近く前に開催された東京オリンピックについての本も
あります。併せてご覧ください。
109号 2012/7/20 (江戸東京博物館ニューズレター 129号)
『上野動物園百年史』
パンダの赤ちゃん誕生に喜んでおりましたら、生後6日目に亡くなったという悲しいお知らせが飛び込んできました。飼育にあたられた方々は赤ちゃんが無事に育つように奔走されたことと思います。本当に残念です。
上野動物園は今年で開園130周年。今から30年前に発行された『上野動物園百年史』には、明治15年(1882)に日本初の動物園としてスタートして以来、上野動物園にやってきたさまざまな動物のこと、100年の間に起こった悲喜こもごもの出来事が記されています。
黒ヒョウ脱走事件、戦時下の動物園、お猿電車の登場、パンダブーム…。中には、インドからやってきた人気者の子象、ジョンとトンキーに芸をさせようと雇い入れたインド人のゾウ使いが、実は、変装をしたロシア人だった、なんていう大正時代の珍事件も記載されています。
各時代の写真や園内案内図をたどるだけでも楽しく、たくさんの人で賑わい発展してきた動物園の歴史をうかがい知ることができます。
本編と資料編の2冊組。資料としても読み物としても、充実している本です。
『上野動物園百年史 [本編]・資料編』
(東京都恩賜上野動物園編集・発行 1982年 C36/4807/2-1,2)
(関連リンク)
上野動物園公式サイト
http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/![]()
108号 2012/6/15 (江戸東京博物館ニューズレター 128号)
『蔵のなか 市政専門図書館蔵書紹介1』
日比谷公園の一角にある市政専門図書館をご存じでしょうか。公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所(旧財団法人東京市政調査会)が運営する都市問題・地方自治に関する専門図書館です。設立は大正11(1922)年と古く、昭和16(1941)年に一般公開されました。そんな市政専門図書館が『都市問題』(後藤・安田記念東京都市研究所刊)に連載する「蔵のなか」が、このほど一冊にまとまりました。
市政専門図書館が所蔵する資料の一部を採り上げ、その内容解説や現代的意義について紹介しています。その中には私たちが聞き慣れない言葉もあります。
例えば「愛市運動」とは何でしょう。「愛市ガール」とは?それを解明するには『東京における愛市運動』(東京愛市聯盟残整理所 1937)の項をご覧ください。
東日本大震災以降、利用者が増えたと言う市政専門図書館。混沌とした現代社会だからこそ、過去の「蔵のなか」に明日への教えが眠っているのかもしれませんね。
『蔵のなか 市政専門図書館蔵書紹介1』
(東京市政調査会市政専門図書館編 東京市政調査会 2011 3187/95/0001)
公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所(旧財団法人東京市政調査会)
http://www.timr.or.jp/![]()
107号 2012/5/18 (江戸東京博物館ニューズレター 127号)
『明治・大正・昭和の新語・流行語辞典』
「板垣死すとも自由は死せず」、板垣退助が刺客に襲われたときに発したとされるあまりにも有名な言葉です。しかし、実際にはこの言葉はなかったという説を聞いたことのある方もいるのでは?『明治・大正・昭和の新語・流行語辞典』(米川明彦編著・三省堂・2002)を何の気なしに開いたときに、この言葉が目に留まりました。
本書は明治~昭和時代の各年ごとに流行語を掲げ、当時の資料と用例を載せています。明治時代までさかのぼっているところと、その根拠となる用例が示されているところがユニークです。
板垣の遭難は明治15(1882)年4月6日のことですが、同年4月11日付『朝日新聞』に「頭を回して徐かに曰く嘆き玉ふな板垣は死すとも自由は亡びませぬぞト」とあるそうです。この言葉、あるいはこの記事がもとになってひとり歩きしたのでしょうか?
106号 2012/4/20 (江戸東京博物館ニューズレター 126号)
『日本の大工道具職人』
東京スカイツリーの開業も間近となりました。
日本の建築技術は世界でも最高水準を誇るといわれています。
地震国でありながら、江戸時代以前からの建造物も残っていることには、驚かされます。
そのような素晴らしい建造物を造り上げる技術と、それを支えるには、優れた大工道具も必要でした。
『日本の大工道具職人』(鈴木俊昭 著,財界研究所)は、江戸・東京を中心に会津ほか日本各地の大工道具職人について記述されています。
著者は、金物店のご主人。大工道具の収集や名人・名工の調査を行い、この業界の方ならではの情報収集と語り口でまとめあげられている好著です。